職務著作
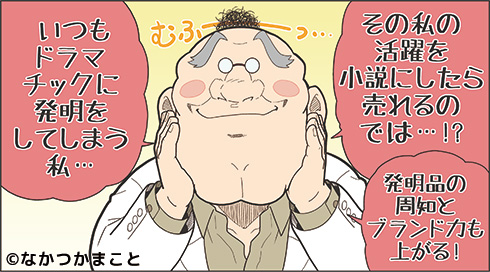
※こちらの情報は2024年8月時点のものです
物価高が国民の生活を直撃しています。スーパーや小売に並んだ商品から企業間で取引される商品までありとあらゆる商品の価格が上昇しています。先日もガソリンスタンドに行きましたが、レギュラーの値段が何年か前のハイオクの値段と同じでした。今の円安が続く限り物価の上昇はまだまだ続きそうです。物価上昇で国民の購買意欲が低下すると景気に悪影響が出るのは間違いないですが、日銀はどう考えているのでしょう。さて、今回のテーマは職務著作です。
職務著作(法人著作)
著作者とは、本来は実際の創作活動を行った自然人ですが、創作活動を行う個人以外が著作者となる場合があり、これを職務著作と呼びます。
著作権法第15条には、職務著作について以下のように規定されています。
「法人その他使用者(以下この条において「法人等」という。)の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物(プログラムの著作物を除く。)で、その法人等が自己の著作の名義の下に公表するものの著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。」
絵画や音楽の著作物は通常、画家や作曲家などの個人によって創作されるものであり、その場合、著作者は個人となります。これに対して、職務著作においては、会社等が著作者となります。つまり、会社の命令に基づいて従業者が職務上作成する著作物を職務著作といいます。例えば、新聞の記事であれば、記事を書いた記者ではなく、新聞社が著作者となり得ます。公務員が作成した報告書などは国が著作者となり得ます。ソフトウェア会社において、会社の方針に従って複数の従業員によりプログラムが開発された場合などにおいて、そのプログラムが職務著作となり得ます。
職務著作が認められるための5要件
職務著作が成立するための要件は、次のとおりです。①法人その他使用者の「発意に基づく」こと。②法人等の「業務に従事する者」であること。③「職務上」作成する著作物であること。④法人等が「自己の著作の名義の下に公表」するものであること。⑤作成の時における「契約、勤務規則」その他に別段の定めがないこと。
発意に基づくとは、法人等が企画、構想した著作物の具体的な作成を命じたことを意味します。法人等の業務に従事する者とは、一般には法人等と雇用関係にある者を意味し、パートタイマーや派遣社員を含みます。職務上作成する著作物ですので、従業者が業務時間外に趣味で作成した著作物は含まれません。著作物が作成した業務従事者の名前で公表されている場合は職務著作として認められません。ただし、プログラムの著作物については④の要件は不要とされています。①~④の要件を満たしても、雇用契約などで著作物の著作権は作成者に留保するなどと定められている場合には、職務著作とはなりません。
特許との違い
法人等において従業者が特許発明を創作する場合があります。特許発明の場合には、必ず従業者(自然人)が発明者となります。殆どの場合、会社が従業者から特許を受ける権利を承継し、会社が特許権者となります。しかし、あくまでも発明者は発明をした個人です。この点が職務著作と大きく異なります。

■サービスのご紹介
企業の総合病院?シーエーシーグループ/TSCでは、経営者様のあらゆるニーズに各分野の専門家がワンストップサービスでお応えします。
人事・労務・経理等のアウトソーシングを是非ご利用ください。
■企業の総合病院?シーエーシーグループ
https://www.cacgr.co.jp/

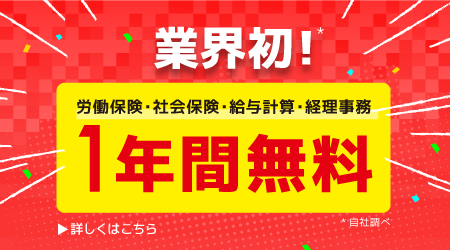
.png)

