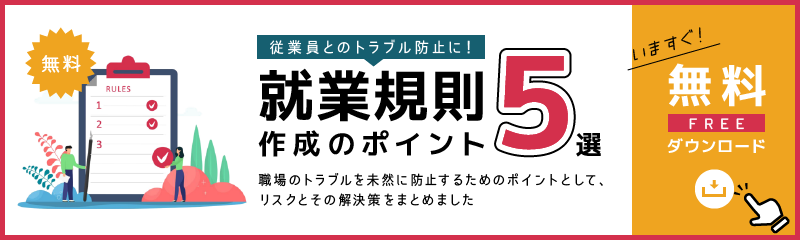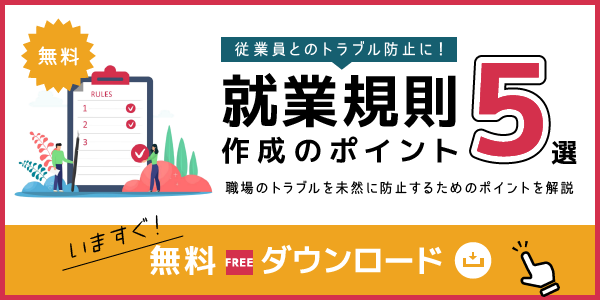【Q&A】半日有給を取った日の残業代の計算方法は?
※こちらの情報は2024年9月時点のものです
Q.相談内容
先日、午前の半日有給を取得し、午後の始業時刻から出社した従業員がいます。その日突発的な業務が発生し、その従業員が2時間の残業を行いました。この2時間については、割増賃金を支払う必要があるのでしょうか?
A.回答
半日単位年休の概要について
半日単位年休とは、本来、年次有給休暇は1日単位で取得することが原則ですが、従業員が半日単位での年休取得を希望してその時季を指定し、それに対して会社が同意をすれば、従業員は半日単位で年次有給休暇を取得することが可能というものです。つまり、会社の判断で、応じるかどうかは決めることができるようになっています。会社の判断というのは、労働基準法第39条において、「労働日」という文言を使用し、労働日単位を表している関係から、労働者が半日単位で請求しても、使用者はこれに応じる義務はないと解されているためです(昭24.7.7 基収第1428号、昭63.3.14 基発第150号・婦発第47号)。ただし、本来の取得方法による年次有給休暇取得の阻害とならない範囲内で運用される限りにおいては、むしろ年次有給化の取得促進に資するものとして考えられています。また、この半日単位の年次有給休暇の取得については、労使協定の締結も不要で、1年につき5日以内という制限もありません。
それでは、ご相談いただいた会社様の所定労働時間を確認しますと、
- 1日の所定労働時間:8時間(9時~18時)、週40時間
- 半日単位年休の所定労働時間は4時間(午前半休の場合:始業時刻14時~終業時刻18時)
18時の終業時刻以降、引き続き20時まで残業した場合、この2時間は割増賃金の支払いが必要となるでしょうか?
この質問におけるポイントは、有給を取得した時間の取り扱いになります。
この場合、労働基準法でいう労働時間は、実労働時間を指しています。つまり、有給を取得した時間については「割増賃金を計算する労働時間には含めない」、ここがポイントになってきます。
そのため、労働基準法第37条が定める時間外労働時間に対する割増賃金の支払い義務が生じるのは、実労働時間が法定労働時間を超えた場合に限られることになり、年次有給休暇を取得した時間分については、割増賃金を計算する上においては除外して計算することができることになっています。
したがって、半日単位年休を取得し、午後の始業時刻から出社して、所定終業時刻後も引き続き働いたとしても、実労働時間で8時間以内ということであれば、労働基準法第37条の時間外割増の必要は無いということになり、この時間が8時間を超えたところから割増は計算すれば良いということになります。
今回のご相談では、半日年休を取得した日の実労働時間は、午後の始業時刻の14時から18時までの4時間と残業を行った18時から20時までの2時間の合計6時間が実労働時間ということになります。法定労働時間の8時間は超えておりませんので、残業申請がなされた2時間の取り扱いについては、割増率を掛ける必要は無く、時間給換算した金額の1倍を2時間分時間外手当として支払えばいいということになります。
ただし、企業様によっては就業規則に実際の労働時間数ではなく、始業時刻の前や終業時刻の後の時間に対して割増率をかけた時間外手当を支払うことを定めている企業様がございます。このような場合には、仮に実労働時間が8時間に達していない状態であったとしても、就業規則の規定の効力が優先されることになり、割増率をかけた時間外手当の支払いが必要となる場合がありますので、半日単位年休の規定がどうなっているか確認しておくことが必要ですので、ご注意ください。
就業規則の作成や変更、規定内容のご相談につきましてはTSCまでお気軽にお問合せ下さい。

■サービスのご紹介
■人事・労務コンサルティング|企業の総合病院®シーエーシーグループ
https://www.cacgr.co.jp/service/consult/
弊社では、働き方改革に関するご相談、また36協定の作成・提出も承っております。
詳しいご相談はお気軽にTSCまでお問い合わせ下さいませ。
■就業規則・36協定届無料チェック|企業の総合病院®シーエーシーグループ
https://www.cacgr.co.jp/clients/service/syugyokisoku/
※閲覧にはIDとパスワードが必要です(会報誌ポケットプレスの裏面をご確認ください)
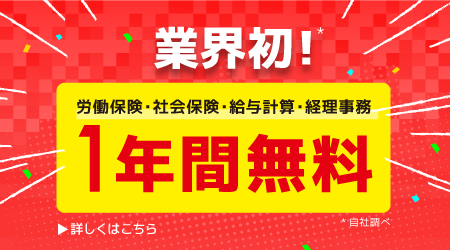
■無料資料ダウンロード