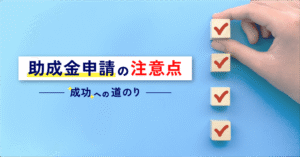超高齢化社会の相続~数次相続の問題点~

※こちらの情報は2024年9月時点のものです
「数次相続」とは、一次、二次と相続が2回以上続いて発生することをいいます。相続が発生し、その相続の遺産分割が確定する前に、相続人の一部が亡くなってしまうことで起こります。たとえば、父親が亡くなった後、母親もまもなく亡くなる場合や、息子も亡くなるといったケースのように、超高齢化社会においては、数次相続が発生する可能性が高くなっています。今回は、このような数次相続が発生した場合の問題点について、2つのケースを想定しながら考えてみましょう。
ケース①
ある夫婦には同居する独身長女と、妻に先立たれたが子供が二人いる長男がおりました。
ある日夫が亡くなったことで相続が発生し、夫の遺産分割の話し合いを始めたところ、独身の長女が親と同居しているのは自分だから、自分が全部相続したいと言い出し、なかなか話が進まない状況になっていました。
そんな中、長男が急死してしまいました。(この場合、夫の相続が一次相続で、長男の相続が二次相続となります。)
相続人である長男が亡くなった場合、長男が持っている夫の相続人としての地位は、長男の相続人である子供二人が引き継ぎます。つまり、夫の相続の話し合いである遺産分割協議には、亡くなった長男の代わりにその子供達が参加しなくてはなりません。
このケースでは、同居人である長女と、長男の子供達との話し合いがこじれることが想定されますし、長男の子供達と長女との関係性が薄い場合、急に相続人として遺産分割協議に参加することになると、連絡を取るのが大変だったり、話をまとめるのにさらに時間がかかったりすることも想定されます。長女が夫の自宅不動産を取得するためには、長男の子供達に相続分相当額の現金預金を渡さないと協議が成立しないかもしれません。
このような数次相続が起きたとしても、一次相続における相続割合に変更はありません。
ケース①では、夫の遺産の法定相続分は妻が2分の1、長女が4分の1、長男が4分の1です。長男の相続人である子供が2名だからといって相続割合が増えるわけではありませんので、長男の子供がそれぞれ8分の1ずつの相続割合となります。
それでは次に、居住用不動産の相続について、起こりうる数次相続の問題について検討してみましょう。

ケース②
両親のうち父親が亡くなった時に、その長男には妻と子供3人がいました。父親の自宅には、両親と一緒に長男家族も同居していました。父親は、自宅不動産については二次相続も考えて、同居している長男に遺贈するとの遺言を残していました。その長男が父親の相続手続中に亡くなってしまいました。長男の妻は夫亡き後に夫の母親との同居を嫌がり、夫の母親が老人ホームに入居することを主張しました。その結果、父親の自宅は長男の妻とその子供達が取得することとなり、母親は住み続けることが出来ませんでした。
このケースの様に、母親と長男の妻子との関係性次第では、母親が自宅を追い出されてしまうといった事態が発生しうることになります。両親ともまさかそんな事が起こるはずがないと思っていたのでしょうが、長男が帰らぬ人となってしまっては、長男の相続人である長男の妻の意向に従わざるを得なくなったわけです。
このようなことが起こらないようにするためには、父親は長男に自宅不動産を遺贈するとしても、さらに母親に対して配偶者居住権を遺贈しておくといった対策を考えておかなければならなかったのです。
今回の事例のように、相続人に高齢者がいる場合には数次相続によって想定外の問題が起こる可能性が今後増えてくると予想されます。相続が発生することにより、仲の良かった親族がもめることもよくあることです。遺言書を作成しておくこと、配偶者居住権を主張できるようにしておくことなど、対策はいろいろありますので、生前に専門家に相談することが大切です。


■サービスのご紹介
企業の総合病院?シーエーシーグループ/TSCでは、経営者様のあらゆるニーズに各分野の専門家がワンストップサービスでお応えします。
人事・労務・経理等のアウトソーシングを是非ご利用ください。
■企業の総合病院?シーエーシーグループ
https://www.cacgr.co.jp/

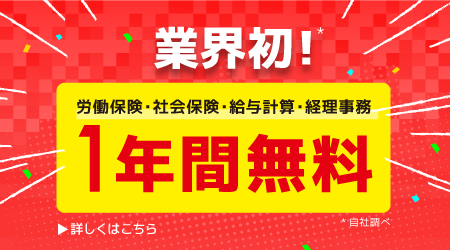
.png)